今日は、家族で、生田緑地内にある「岡本太郎美術館」に出かけてきた。開催中の展覧会「岡本太郎と太陽の塔〜万国博に賭けたもの」を見るためだ。この展覧会とともに、約3時間にもわたる大阪万国博覧会長編ドキュメンタリーも見てきた。
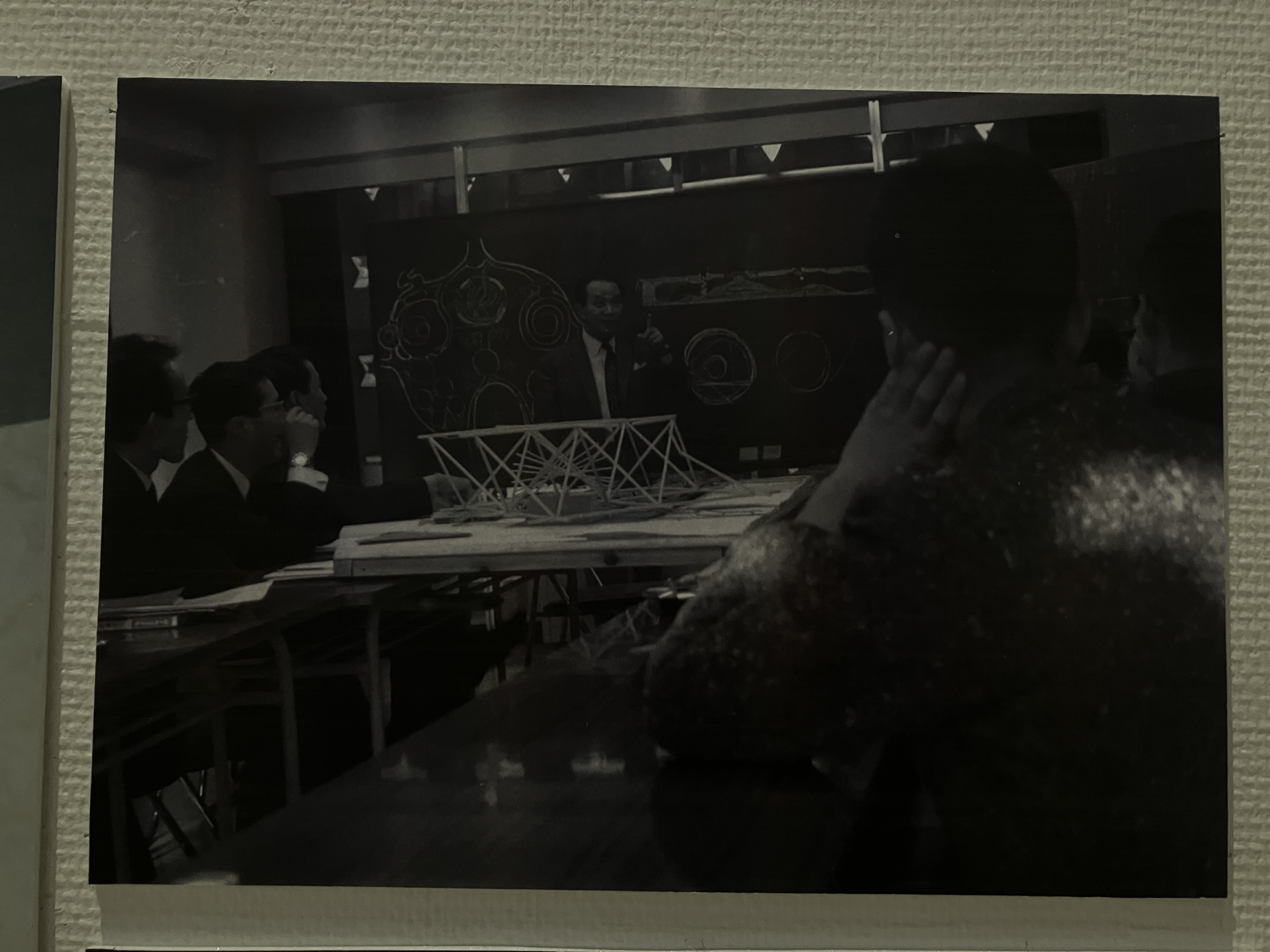
開会式で、子どものようにはしゃぐ丹下健三の姿が印象的だった。本当に嬉しかったんだろうな。やりきったのだろうな。また、携帯がなかった時代、「迷い大人」がたくさん出たのだそうだ。今となっては笑い話。
1970年の大阪万国博覧会協会長は、石坂泰三。そう、城山三郎氏が「もう、きみには頼まない」で描いた石坂泰三だ。まず驚くのは、万博準備に相当なお金を使わせていること。
岡本は、準備のために、ヨーロッパだけでなく、アジア・アフリカ諸国に出かけ、世界中を歩き回って、さまざまな文化的民俗学的な品物を持ち帰り、自らのインスピレーションの源泉とした。
岡本が持って帰ったさまざまなお面などの品は、太陽の塔でも使用された。その莫大なコレクションは、現在の国立民俗学博物館の発足につながっている。
やることがチマチマしていないぞ!
岡本は、世界中を旅する中で、世界中の無名な人々が支える生活、文化といったものから、命の根源を掴んでいく。
岡本太郎の人生そのものがとてもユニークだが、その稀有な「岡本太郎」の存在無くして、1970年大阪万国博覧会の成功はなかったと言える。
当時の誰もが「本物」で勝負しようと格闘したのだということを強く感じる。その迫力、パワーを感じた。
私は、昨年、家族で太陽の塔を訪れ、その内部も見学してきた。この太陽の塔が国の重要文化財に指定されることが決まったという。当然だ!喜ばしい。
なぜなら、太陽の塔は、その建物に力があるというだけではない。つまり建物の価値だけではなく、そのコンセプトに、一貫した人類への眼差し、生命の根源、哲学が表現されている。だから価値があるのだ。そこが、2025年の大阪万博で、木製の大屋根リングを残すのとは訳が違う。
我が家がハマっている縄文文化を再評価した一人が岡本太郎。
彼の語ったことが、今もなお、私たちの心に響く。



コメント