生活クラブ風の村わらしこ保育園が20周年を迎えたとのこと。
おめでとうございます。
無認可の時の園長のご挨拶に、「大きな事故もなくここまで来れたこと」とあったけれど、本当にそう。息子も、わらしこで「人としての土台」をつくってもらった。体、舌(食事)、人とのかかわり、がんばり、想像以上の存在に育ってくれた根っこには、わらしこで育ててもらった土壌があると確信している。関わってくださった、すべての皆さん、子どもたち、保育士をはじめ職員の皆さん、保護者の皆さん、地域の皆さん、生活クラブの皆さんに本当に感謝している。
その記念講演会があるとのことで、参加してきた。
東京子ども図書館理事 杉山きく子さんの講演。
「絵本とおはなしで子育てを楽しく!」
私も、よく夜寝る前に、読み聞かせをした。時には、子どもより早く寝落ちすることもあったような・・・(笑)。息子の通った小学校では、6年間読み聞かせの活動をしてきた。息子は、それほど、本好きに育ったわけではないけれど、ぽつんぽつんと、絵本ででてきたことを話すことがある。
講演会から帰ってきて、息子に「絵本を読んでたこと覚えている?」と聞くと、「覚えてる」と。ホッ。
「今でも覚えている本は?」
「やまたのおろち、スーホの白い馬(保育園でもいっぱい読んでもらった)、たつのこたろう、ぐりとぐら、エルマーの冒険、木を植えた人、かいじゅうたちのいるところ・・・かな。」
杉山さんは、「読書は評価できない。効果が見えないことこそ、読書のすばらしさ。」とのこと。
国語力のためとか、本好きになるとか、親の下心(笑)のためには何もならないと思った方が、よさそうだ。でも、子どもたちが、親から受け取る物語の面白さ、ワクワク感を楽しむ、親を独占できる時間、それが一番のようだ。
参考になったのは:
ー大人がいいと思う絵本と、子どが好きなものは違う。
ー長く読み継がれてきたものは不滅。今の子どもたちも大好き。
ー小学生にも読み聞かせを!もういいと言うまで続けては。
ー最初から最後まで読まなくていい。最後まで読むことにこだわらない。
ー人の話を聞いて理解する能力がつくのでは?
ー親が即興でつくってみるというのも楽しい。
ー絵本は、それ一冊で芸術品。演劇風にあまり飾り立てる必要はない。
ー子どもの力を信じる
ー障害をもっている子、動いている子も、ちゃんと聞いている。
即興で話をつくるというのは、いいな!と思う。もっと早く知りたかった!いま、高校生に向けて物語をつくると、どうしても嫌味になりそう(笑)。気をつけねば!
あるお父さんから、「本を読む時に、役者のようにいろいろと演出することがあるけれど、どんな楽しい読み方があるか?」という質問があった。
杉山さんからは、「絵本はそれ自体が芸術品。何も演出しなくても、それをそのまま読むだけで、子どもたちは引き込まれる」とのこと。印象的だった。
私も、「トマトちゃん」や「かいじゅうたちがいるところ」は、演出つきで読んでいたことを思い出す。息子は、キャッキャッと喜んで、私も嬉しかったけれど、今聞くと、覚えていない・・・・と(笑)。自分も楽しく、子どもも楽しければ、演出ありの読み聞かせもいいと思う。でも、覚えてないかも(笑)。
障害をもつお子さんも、絵本はとても楽しいと思う。重い障害のある子に、1、2、1、2の絵本はどうかという話もでたが、子どもたちの知性はそんなものではない。「この子には、これくらいの本」と、大人たちが考えないで、どんどん、ストーリーがあるもの、主人公が行動する本、子どもたちはちゃんと面白さをわかっている。絵本の中で、わくわくする体験を楽しんでくれるだろう。
小学校で読み聞かせを続けた。先生が、きちんとさせようとするクラスもあったことが気になっている。あまり気にしなくていいのでは?確かに、騒がしいクラスは、読み手の力が試されるけれど。読み手がしっかりしていると、子どもたちは、本当に集中して聞くようになる。ただ、体が動く子どもも、しゃべる子どもも、実はよく聞いている。私は、読み聞かせは、子どもたちが体も心も自由にする時間であってほしいと思っている。
以前ブログでも書いたことがあるが、調査によると、0歳から6歳までの子どもの1日のインターネットへのアクセスは100分とのこと。決していいことと思わない。杉山さんは、そのうちの10分でもいいから、絵本を読んでほしいとのこと。私も、PCや携帯の画面より絵本の方が目に優しく、子どもたちの体と脳にちょうどいいと思っている。
最後に、苦しい時にも「本」があると思ってほしい、とのこと。その通りだと思う。色々なことがあった時、本は、いろいろな助けになる。知識を得るだけではなく、主人公の思考と対話することができたり、その中で、自分の問題や自分が何かに向き合う手助けになってくれたりするだろう。人との対話、本との対話があることが、自分の人生の一助となることを忘れないでほしい。
こどもたちよ
子ども時代をしっかりとたのしんでください
おとなになってから
老人になってから
あなたを支えてくれるのは
子ども時代の「あなた」です。
石井桃子 2001年7月10日
流山市も大きく変化する中で、流山に育つ子どもたちが、
「しっかりと、子ども時代をたのしめる」環境を整えることが、
流山に暮らす大人に求められているのだと思う。



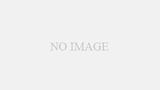
コメント