3月30日(日)、東京・青山に結集したのは、農業従事者の皆さん、トラクター、そして日本の農家・農業を応援する人たち。

写真に写る「流山」の文字???
そう、真澄屋農園の吉田篤さんの勇姿!
愛用のトラクターと共に写るメッセージには、「百姓は国の宝 本気で守れ」の文字が。
その通り!
日本だけではない。今、世界中で、命を支える農業従事者たちが、「これでは生活できない!」と声をあげ、各地でトラクター・デモが起きている。
気候変動の中で、従来の収穫ができなくなっている地域が出てきている。
日本では米価が高くなり、人々は、どうしたものかと考え始めているが、単に「米価が安くなればいい」と思っていないだろうか。
鈴木亘弘東京大学大学院教授は「農は国の本なり」と熱く語る。
その通り!
食料自給率がカロリーベース(消費された食料のうち、国内で生産されたものがどれくらいあるかを表した割合のこと)で38%と言われる中で、今、日本は、日本の農業の歴史、現況、制度、構造をしっかりと確認しながら、本気で議論し、日本の農業を「改善」しなければならない時にあると思っている。
・農業従事者数の減少と高齢化
・農業収入の少なさ
・輸入に頼った農産物:気候変動等のため輸出国の農産物が減少した場合、輸入できなくなる。
・種子法の問題:野菜の種子の9割が海外からの輸入に頼っており、これが止まったら何も作れない。
・戸別所得補償制度、経営所得安定政策の拡充
・他国と比較してもかなり少ない食料備蓄
・生産資材の高騰:トラクターなどの機材、重油、肥料
・農薬による健康被害
などなど。
鈴木宣弘先生が流山市で講演された際に、井崎市長が流山市における農業が一面に書かれた「2025年1月1日号広報ながれやまを見てください!」と話されていたが、井崎市長の市長在任期である1994年から2021年にかけて、田は3分の1、畑や森林は2分の1に減少した。この事実と責任は、非常に重い。
流山市は、年間の学校給食用の米を流山市だけで調達できないはずだ。物流センターを誘致して年間8億円の税収を得たが、流山市民は、流山市内における貴重な田を未来永劫失った。
鈴木先生は、「地元のものを地元で食べることを支えるしくみが必要。」と語り、自分たちが暮らす「流山から命を守る政策の強化が必要」と語る。
その通り!
そして最後に、鈴木先生のこの言葉を紹介したい。
「コストがかかっても支えることが、命の安全保障なのだ。」
この言葉は重い。
トラクターデモ。
これが世界中の農業従事者と連帯しながら、足元のローカルにおける確実な収穫へとつながり、農家の皆さんがきちんと生活できる経済的支援を実行することにつながることを願ってやまない。
そのためにも、この国の政府と自治体の命に対する、農業に対するマインドが変わらなくてはならない。



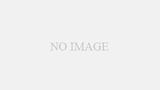
コメント